沖縄空手道の沿革
沖縄は島国であり、人口は多いが資源に乏しく島民は昔から孤島苦を味わってきた。
しかしながら不撓不屈の精神に富んだ彼らは環境に屈することなく、勇敢にも海外に
進出を試みた。
昔は、北は日本本土・朝鮮・支那、南はジャワ・スマトラ・インドネシアにかけて交易を
行い、発展し多くの文化遺産を残しました。
そこで、このような国情から島内においても、また、海外に出ても自らそれぞれの交易に
必要な諸徳が宿命的に生じた。凡そ海外発展の手段には相手国との間に戦争か、
平和的手段かの二つの関係が生じるものと思われる。しかし沖縄の人々は平和交易
の道を選択した。
だからこそ彼らが相手に愛され成功の鍵を握ることができたのでした。
しかるに時々思いがけない迫害に逢うことが無いわけではなかった。
このような時に彼らは常に平和にいきながらも、決して尚武の精神を忘れなかった。
そうかと言って身に寸鉄をも帯びない彼ら、いかにしてこの鉄火の渦に抗することが出
来たであろうか、それは言うまでもない空手術という空拳よく、武器を制する正当防衛
の術を心得ていたからです。
平和の為に舞を舞う彼らの手と足がいざ防衛となるや武器に早変わりして空手術の
本領を発揮しました。
だが相手の武器に対しては彼らも武器を用いる事もあった。それは三線を武器にして
木刀の代用としたり三味線の糸巻きを飛び道具とすることである。
空手発達の要因に1448年尚真王の世界に魁けた武器廃止や「慶長の役」後一
切の武器がとりあげられたことが言われていますが、これらの事は空手発達の一因に
は相違ないが多くは昔から彼らの生活の中におりこまれていた。
近代空手道の発達 (首里手 糸洲安恒先生・那覇手 東恩納寛量先生)
沖縄においては人民の武器を持たない事が空手道の発達を促進させた。従来空手
は単に「手」と呼ばれていた。
一方中国から伝わった「手」に『唐手』(トディー)と言われるものがあり、明治になって
中学校に体育として採用されるようになると、「手」も『唐手』(カラテ)と称された。
しかし、昭和になってからは中国拳法である『唐手』(トディー)と誤解される事を避ける
ために徒手空拳の意味から「空手」と命名され、今日に至っている。
空手武術家の事を武士と尊称したが日本の武士の意味とは少し異なる。
沖縄において、空手は主として士族階級の間に行なわれ、棒やサイ術等の器物は、
多くの場合平民が使用した。
そして武術を知らない強力者や喧嘩上手の人は「チカラ」とか「オーヤ」(闘争者)
「ウマイ」(蛮勇)等と軽称され区別された。
空手の発達を地区別にみると、首里泊、那覇が盛んで首里手、那覇手と称された
が、これは流儀ではなく派別とでも言うべきものであった。
手法は東恩納寛量先生の時代から那覇手は剛柔流(命名は後世)となり、首里手
は少林流(命名は後世)となった。
かくしてここに空手の名人も数多く輩出したが中興の祖として仰がれたのは首里手の
糸洲安恒先生と那覇手の東恩納寛量先生ので双璧でありました。
明治の末ごろ糸洲先生は首里の師範学校や中学校に、また、東恩納先生は那覇
の警察学校や中学校に共に空手を体育科の中に正課として採用され指導された事
が、昔の武術から脱し武道として体育化されて今日の普及発達をみるに至った主因
である。
私たちは空手度を学ぶものとして、この二人の拳聖を永久に忘れてはならない。
 |
剛柔流について 剛柔流流祖 東恩納寛量先生 |
剛柔流の流祖、東恩納先生の前には那覇には首里手と区別されるほどの特色
のある流儀はなかったようだ。
東恩納先生もそんな雰囲気の中で幼少から空手を修得されたのであったが、先生が
中国の福州に渡って中国拳法を学び、帰郷後、中国の拳法に従来の「手」の良さを
加味して郷土に向くように創作されてから、之の特色も現われ、那覇で指導されたこと
から、はっきりした那覇手として首里手と名実ともに違うようになった。
しかし先生は流名をつけたのではなかったが剛柔流の「流祖」とすべきである。
次に昭和三年に御大典の奉祝全国武道大会に各地の武術代表が京都に集め
られたとき、東恩納先生の高弟宮城先生が選ばれたが、都合あって宮城先生の弟
子新里仁安氏が代表で行った。
そのときに集まった代表選手は皆堂々たる流名を持つ武術家であり、もし流名をもって
いなかったら素人武術家と誤解されることもあった。
沖縄代表の新里氏は流名を聞かれて当惑した。
これは当時の沖縄の空手には流儀名がなかったからです。
ところが流儀がないと答えると権威に関するので突然に「半硬流」ですと答えて、その
場を取り繕った。帰郷後にそのことを宮城先生に申し上げたら、それはもっともだと思わ
れ中国の拳法八句中「法は剛柔を呑吐し・・・・・」
と言う句から取って剛柔流と命名した。これが空手界での流名の始めです。
中国福建少林拳白鶴門の伝書であります武備誌の 「拳法之大要八句」
人心同天地 血脈以日月
法剛柔呑吐 身髄時応変
手逢空則入 碼進退離逢
目要視四向 耳能聴八方
剛柔の解についても社会の秩序はすべて剛柔の精神で保たれており、礼儀も剛柔の
現われです。
また、世渡りについても堅いばかりでも柔らかいばかりでもいけなく、剛毅と柔順の調度を
使い分けることによって、その人を大成させるものだとした。
更に空手を技術的にみても準備や受けの時は力を抜いて柔にすると同時に息も呑に
し、反対に突きの場合は力をこめて剛にし息を吐くと言う剛柔の備わりがこの剛柔流の特
色であるとした。
 |
剛柔流開祖 宮城長順先生 |
1888年に那覇市に生まれて那覇市で育ち、1953年に那覇市でなくなられた。体型
は大型ではなかったが、筋骨たくましく眼光炯炯(けいけい)として、見るからに偉丈夫な
観相を呈していました。
先生は財力も相当あったので、生活に不自由なく一生を学問的に武道に打ち込んで、
先師の道を引き継いで、開拓発展させたのは、この人の右に出るものはなかった。
先生がかってもらした言葉の中に「自分のもつている時と金を、もし何かの事業につぎ込ん
だにしても成果をあげたであろうが、自分は東恩納先生の奥義を究めるために生涯を捧げ
た」と、また、先生はついに自宅に師をおまねきしてまで苦心惨憺、師の持てる総てをしつく
さねば止まなかった。
師亡き後は中国を二回往復して研究を続け、文献を集めたりした。
更に日本本土や米国ハワイまでも渡航、普及されたことは空手の国際化の魁けでありまし
た。
昭和八年京都で大日本武徳会(戦前最高の武道団体)が開かれるや先生は沖縄武
術家の代表として出席され空手道概説を提出され、実技を公開して日本武道の一つとし
て空手道が認められた。
そしてこの功績により空手界から始めて武徳会より空手道教士の称号を授けられた。
先生は武術の習得もさることながら先生の功績は空手の組織的指導化にあり、即ち空
手の中に準備運動、補助運動、普及型、基本形整理運動を編み出し指導上に画期的
な功績を残された。
既にこれを学校や警察に実施して一般社会への普及を促した。
当事の世人は空手をやると貧乏人になったり、喧嘩好きになると言って敬遠する者も多か
ったが先生のこの努力が功を奏して社会大衆に体育として正しい認識を与えた。
流派を超越した話があります。或る日、先生は首里手の総帥糸洲を訪ねて指導を乞うた。
そうしたら糸洲先生は「君は既に東恩納先生の高弟であり、最早上達の域に達しているか
ら私の指導を受けるには及ばない。
私の技を見れば分かるよ」と言われ実技を指導することはなかったが、その後しばしば糸洲
先生のお宅を訪ねて研究を続けていました。
先生が創作されました普及形の撃砕第一、撃砕第二の形は剛柔よくちょうわされており初
技は首里手の剛を思わすのがあるのも、うなづかれる。
渡口先生に対する指導は十代、二十代は理論を教えず、もっぱら体をつくることと技を練
ることに重点を置き三十代過ぎからは全く変わって「君は既に一家を持ち酒も煙草もたしな
んでいるから、最早得る時期はすぎたので此れからは理論と指導法を習得するべきだ」と
言われ、新時代に適応する指導法、普及形創作と見解、指導技術と理論を説かれるの
であった。
先生の齢も還暦を過ぎ天命を予知されてか、学習のため師宅へ伺うと短くて四時間、長い
時は昼から夜中まで飽きずにじゅんじゅんと説かれたのには恐縮しました。
それでも私は真剣にならざるをえなくなり、行きがてらの寄り道の用事等を忘れて、いつも家
族に怒られる始末でした。
話題がだぶって私が又かと言う顔付きをすると「同じ話でも二十代と聞くのと三十代で聞く
のとではその感受印象と理解が異なるが、それが秘伝だよ、また、いかなる良説でもそれを
実行しなければ何の効果もない」と言われた。
それによって渡口先生も空手に対する理論を体得し、見識を広めそして今日、創作理論を
実地に応用することが出来たのもそのお陰である。
もし鍛錬の一方の習得だけに終わっていたら教わっただけを子弟に相継ぐ中継役に止まり
何らの新機軸を開拓する意図も生まれなかったでしょう。
以上、記した様に我々は他の道場に勝る立派な伝統を持っている。この誇りをもって尚礼
館空手道に励み、此れを日常の生活の中に生かし、個人個人が発展することが尚礼会
(尚礼館空手)の発展につながると思います。
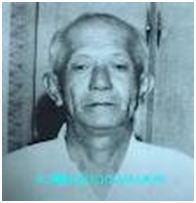 |
比嘉世幸先生 |
明治31年11月 那覇市にて出生、
明治44年 十三歳の時東恩納寛量先生について師事したが、師亡き後、宮城
長順 先生に教えを受け、多年にわたり研鑽を積まれた。
大正8年 沖縄県立水産学校を卒業、小学校の教員に奉職した。
大正9年 警察官に転職。
昭和6年 空手道場設立のため退職。
昭和8年 那覇市松下町に剛柔流空手研究所を設立。
昭和9年に 第一回武徳祭演武大会において演武を披露され、鈴木壮六氏
(大日本武徳会)よ り表彰されました。
昭和15年5月 安正王殿下より錬士の称号を授与されました。
昭和25年 那覇市与儀に尚道館をせつりつ、弟子の指導に専念された。
昭和29年 大日本武徳会から範士号を授与されました。
糸満高校・琉球大学・沖縄刑務所において指導なさいました。
昭和41年4月 16日 逝去されました、68才。
先生の生涯の大部分は宮城長順先生のかげにかくれて一生を過ごされたことが多いようです。
比嘉先生は人生を達観したような無欲の人でありました。ちょうどお坊さんのような方であり、特別
な武勇伝のないところが武勇伝であります。
先生はひとたび道場の練習になると厳しいが、普段はいつも笑っていらっしゃって大声を出した
ことがありません。
痩せ型で筋金ばかりといった方が良い方で、身長165センチメートルでした。先生は空手一筋
でした。
終戦後、奥様が亡くなられて後は先生はお一人で、渡口先生の家で一緒に暮らされたこともあ
りました。
戦後最初(昭和二十二年)の道場を造って生活をなさいました。
昭和四十四年に比嘉世幸先生を偲んで追悼演武会が行なわれました。その際、比嘉世吉
(世幸先生の長男)先生のお宅で幹部の方が参集してくださって座談会が行なわれました。
その席上高嶺朝睦会長のお話で印象に残ったお話を紹介します。
「先生は非常に物事に動じなかった。そして非常に寛大な方でありました。戦前の空手の鍛え方
は、基本三戦から二ヵ年位して開手型セイインチン・セーパイとひとつずつ習っていった。
とにかく基礎を主にして約束組手へ進み、七.八年熟練した連中は自由組手をした。
だからケガはしない、とめる技量ができるから」このお話は、空手道を修練しているものが相手に
怪我をさせず、同時に相手に対して粗暴な振る舞いをさせないという、『教え』を含んだ言葉と感
じました。
「尚礼館」名の由来
儒教のなかに「仁・義・礼・智・信」と言うことばがあります。沖縄には儒教の教えとは異なりま
すが、礼を重んずる心があります。
道徳の基本としての「礼」をいかに重くみているかは、尚王家の城門に掲げられた額の文字
「守礼の門」によっても理解できます。
近年(昭和三十三年)には、切手の図案として用いられ、「守礼切手」として広く人気を集め
ているのも、偶然のこととはいえ、現在の日本の世相を考えあわせると皮肉な感じがしないで
もありません。
広義にに解釈していけば、「礼」は「仁・義・礼・智・信」のすべてをひとつの文字で代表させた
と考えても決して過言ではありません。
沖縄は尚王家の時代、武器の撤廃による平和友好政策をおし進めました。
その理念とする「守礼」の文字は一貫してその意味も解釈も変わってはおりません。
もちろんそれが当然なことなのでありますが、それすらおぼつかない現代では、逆に珍しい事と
もいえます。
しかし私たちはそれを誇りとし、理想として高く掲げて止まないのです。
今日の日本は、過去の沖縄のたどった歴史をそのままにここまでまいりました。
過去の武力に頼った失敗は、「礼」に置き換えられることによって、更に今後の大きな発展を約
束するものと考えたいのです。
そのような意味からも、私たち沖縄の誇りとする「礼」をとって「尚礼館」と名づけたのです。
尚礼館空手を学ぶ者はこのことを忘れずに努力を続けて欲しいと思います。
尚礼館創設者 渡口政吉先生
大正6年5月 沖縄県那覇市にて出生
昭和8年3月 剛柔流流祖宮城長順の弟子比嘉世幸の道場に入門、そして宮城
長順先生に教えを受ける
昭和17年4月 南スマトラ・バレンバン製油所に軍属として勤務。その間、軍人および
現地人に空手を指導
昭和21年 終戦により糸満市に復員
昭和22年10月 恩師 比嘉世幸先生の媒酌により結婚
昭和23年 糸満地区体育修練会空手部師範
昭和27年 剛柔流振興会結成(会長 宮城長順先生)
常任理事に就任
昭和28年 宮城長順先生死去により、剛柔流振興会を空手道剛柔会に改称、
(会長比嘉世幸先生)
副会長に就任
昭和29年 空手道剛柔流研究所「尚礼館」創立
昭和31年5月 沖縄空手道連盟結成、理事に就任
昭和33年 奄美尚礼館創立
昭和33年7月 全沖縄体育祭で空手道演武(於 コザ市=現沖縄市)
昭和34年 コザ中学校図書館建設協賛チャリティー空手道演武大会主催
昭和35年4月 南極観測船「宗谷」歓迎会で空手演武
昭和35年10月 上京、東京代々木修練会空手道場師範
昭和37年 尚礼館目黒道場開設
昭和38年2月 中野区神明町氷川神社に尚礼館開設
昭和38年5月 法政大学剛柔会創立、師範に就任
昭和38年6月 東京都中野区南部公会堂において、
第1回尚礼館空手道大会開催
昭和40年8月 全沖縄空手道選手権および演武大会開催
昭和44年4月 玉野工務店 玉野源吉会長、玉野友哉社長のご協力によ東京本部
道場新築、開設
昭和45年4月 沖縄国政参加祝賀記念大会において演武(於東京)
昭和45年10月 第1回世界空手道選手権大会において参加、模範演武を行なう
昭和47年5月 アメリカ、カナダ、ブエルトリコ巡回指導
昭和49年3月 ヨーロッパ各国およびアメリカ、カナダ巡回指導
昭和53年6月 「沖縄を紹介する夕べ」 東京外人記者クラブにおいて空手道演武
昭和57年9月 カナダ尚礼館十周年大会において指導演武
昭和58年8月 宮城長順先生慰霊三十周年顕彰会および尚礼館創立三十周年記念
演武大会開催
昭和60年7月 アメリカ、カナダ巡回指導
昭和61年 東京都空手道連盟 相談役
東京都中野区空手道連盟 相談役
法政大学沖縄空手道剛柔会 師範
沖縄空手道剛柔流尚礼会 会長
平成10年8月 31日死去 享年81歳
渡口政吉著 「空手の心」より
戻る
トップページへ